サッカー戦術の基本のき:Fijar(引き付ける)と Dividir(離れる)
はじめに:2対1の局面をどう教えるか?

サッカーの戦術を考えるうえで、2対1の状況は非常に基本的でありながら、奥深いテーマです。
その中でも重要なのが「Fijar(フィハール)=引き付ける」と「Dividir(ディヴィディール)=離れる」という概念。
これらはスペインの育成年代でも繰り返し指導されるキーワードであり、指導者として選手に明確に伝えるべき考え方です。
「Fijar(フィハール)=引き付ける」とは?
Fijarとは、相手を自分に引き付ける動きのことを指します。
2対1の状況では、ボールを持っている選手がドリブルで前進することで、相手DFを自分に引き付けることを表します。
ここで相手が引き付けば、味方にフリーなスペースを作り出すことができます。

「Dividir(ディヴィディール)=離れる」とは?
Dividirは、ボールを持っている味方の選手と相手から距離を取る=スペースを確保する動きのことです。
ここでは、進行方向に対して横に広がる動きを表します。
この「分離」の動きがあることで、パスを受けるスペースが生まれます。

この2つの関係性が鍵
プレーの判断の基準①:相手がボール保持者に引きついているか?

相手選手がボール保持者に引きついているのであれば、2対1の状況では必ず「よりフリーな選手」が生まれます。
相手選手を引きつけることができている状況では、よりフリーな選手とプレーをしましょう。
一方で、相手が動かないのであれば、基本的に、ドリブルでボールを前に運ぶスペースがあります。
そのまま前進し続ければ良いのです。
相手選手がボール保持者に引きついているかどうか、これをプレーをしながら正しく分析できるか、その分析をもとに良いプレーの判断ができるかを、指導者は見ます。
プレーの判断の基準②:相手が縦を切っているのか?

先ほどと同様に、これも選手自身がプレーをしながら状況を分析し、より良いプレーの判断をすることができているかどうかを、我々指導者は見ます。
なぜスペイン語で伝えるのか?
「スペイン語の方が短くて伝わる」というのは、実は多くの日本人指導者が感じることです。
- Fijar:「相手を引きつけて、味方をフリーにする」までの概念を含んでいる
- Dividir:「スペースを作ってパスを受ける準備をする」という意味合いを含んでいる
戦術的なコンセプトを短い言葉で繰り返し伝える。これは選手への浸透度を大きく変えるポイントです。
*フィハールは「フィハ」、ディヴィディールは「ディヴィデ」で伝わります。
おわりに
FijarとDividirは、サッカー戦術の基本中の基本。
しかし、基本だからこそ丁寧に、繰り返し、意味づけをして伝える必要があります。
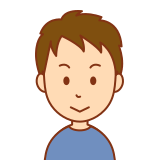
2対1でも、1対1で突破できるなら、突破してまえば良いじゃないか!
これは、アジアサッカーによく見られる考え方です。
我々指導者は、「結果」よりも「過程(プロセス)」に目を向ける必要があります。
なぜなら、“指導者=教え導く者”だからです。
特に、育成年代と言われる現場では「結果」よりも「過程(プロセス)」により目を向けるべきです。
「1対1でも突破できる=結果」です。
我々は、どのように選手がサッカーのフィールド上で状況を分析し、プレーを判断したのか、そのプロセスに目を向けましょう。



コメント