今回はサッカーにおける「ドリブルの使い分け」に焦点を当て、スペインでの指導経験をもとに、2種類のドリブルの違いとその必要性について解説します。
私はマドリッド州で6シーズン、指導者として活動し、スペイン1部リーグのセカンドチームで分析官も務めてきました。
UEFAライセンス保持者として、育成の現場で実際に使われている「ドリブルの概念」を日本の皆さんに共有します。
ドリブルには2種類ある|『運ぶ』と『仕掛ける』
ドリブルはすべて「相手を抜く技術」だと思っていませんか?
実は、ドリブルには大きく2つの役割があります。
- 運ぶドリブル(Conducción / コンドゥクシオン):スペースにボールを運ぶ
- 仕掛けるドリブル(Regate / レガテ):相手に仕掛けて突破を狙う
この2つを状況に応じて使い分けることが、サッカーの現場では非常に重要です。


なぜ、ドリブルを使い分ける必要があるのか?
試合中の判断の違い
以下の2つの状況を想像してください。
- ① サイドで1対1:仕掛けるドリブルが有効
- ② ビルドアップで前方にスペースがある:運ぶドリブルが有効
どちらも「ドリブル」ですが、目的と状況はまったく異なります。
的確な選択ができる選手がいるチームは、試合をより有利に進めることができます。

右図は、ビルドアップにおいて、前方にスペースがある状況です。
左図では「仕掛けるドリブル」、右図では「運ぶドリブル」を選択するべきです。
これが状況によって、使うべきテクニックが異なると言うことです。
練習設計の違い
この2つのドリブルの違いを理解していないと、指導者として練習メニューの設計を誤る恐れがあります。
例えば:
- Aメニュー:スペースを見つけてボールを運ぶ → 運ぶドリブルの練習
- Bメニュー:1対1で抜き去る技術を磨く → 仕掛けるドリブルの練習
練習メニューを作成するとき、「これはどちらのドリブルか?」を明確に意識する必要があります。
どちらの図が、どちらのドリブルの練習でしょう?

Aが「運ぶドリブル」の練習で、Bが「仕掛けるドリブル」の練習です。
練習メニューを例に出した理由は、もし “〇〇ドリブルの練習メニューを作ってきて” と頼まれたときに、これが異なると、指導者として致命的なミスになると言うことを伝えたかったからです。
なぜ致命的なのか?
それは、指導者間でテクニックのワードを共有できていないからです。
選手もドリブルの使い分けを知っておくべき理由
「使い分けを理解するのは指導者だけで十分」と思っていませんか?
実は選手自身もこの違いを理解しておくことで、プレー中の判断ミスを減らすことができます。
例えば、チームメイトに「ドリブルしろ!」と声をかけた時、
- 「運べ(Conduce)」なのか
- 「仕掛けろ(A por él)」なのか
言葉の違いを理解していないと、意図が正確に伝わらず、ミスにつながります。
先ほどのビルドアップの場面で考えてみましょう。

近くにいる選手が「ドリブルしろ!」と言ったとき、ボールを持っている選手が「運ぶ」と「仕掛ける」を混同してしまうと、プレーの判断のミスにつながります。
「運ぶドリブル」と「仕掛けるドリブル」に関して、サッカー指導者だけでなく、サッカー選手もこの違いを理解しておきましょう。
スペイン語のドリブル用語でプレーを明確にする
スペインの現場では、次のような単語が日常的に使われています:
- Conduce(コンドゥセ):「運べ!」
- A por él(ア・ポル・エル):「仕掛けろ!」
もちろん日本語で「運べ!」「仕掛けろ!」でも構いません。
大切なのは言葉を聞いた瞬間にチーム全体で同じプレーイメージが共有できているかどうかです。
まとめ
- ドリブルには「運ぶ」と「仕掛ける」の2種類がある
- 状況に応じて使い分けることで、試合中の判断や練習設計が正確になる
- 選手・指導者ともに、言語でプレーを明確に共有することが大切
ぜひ日々のトレーニングや試合で、このドリブルの使い分けを意識してみてください。
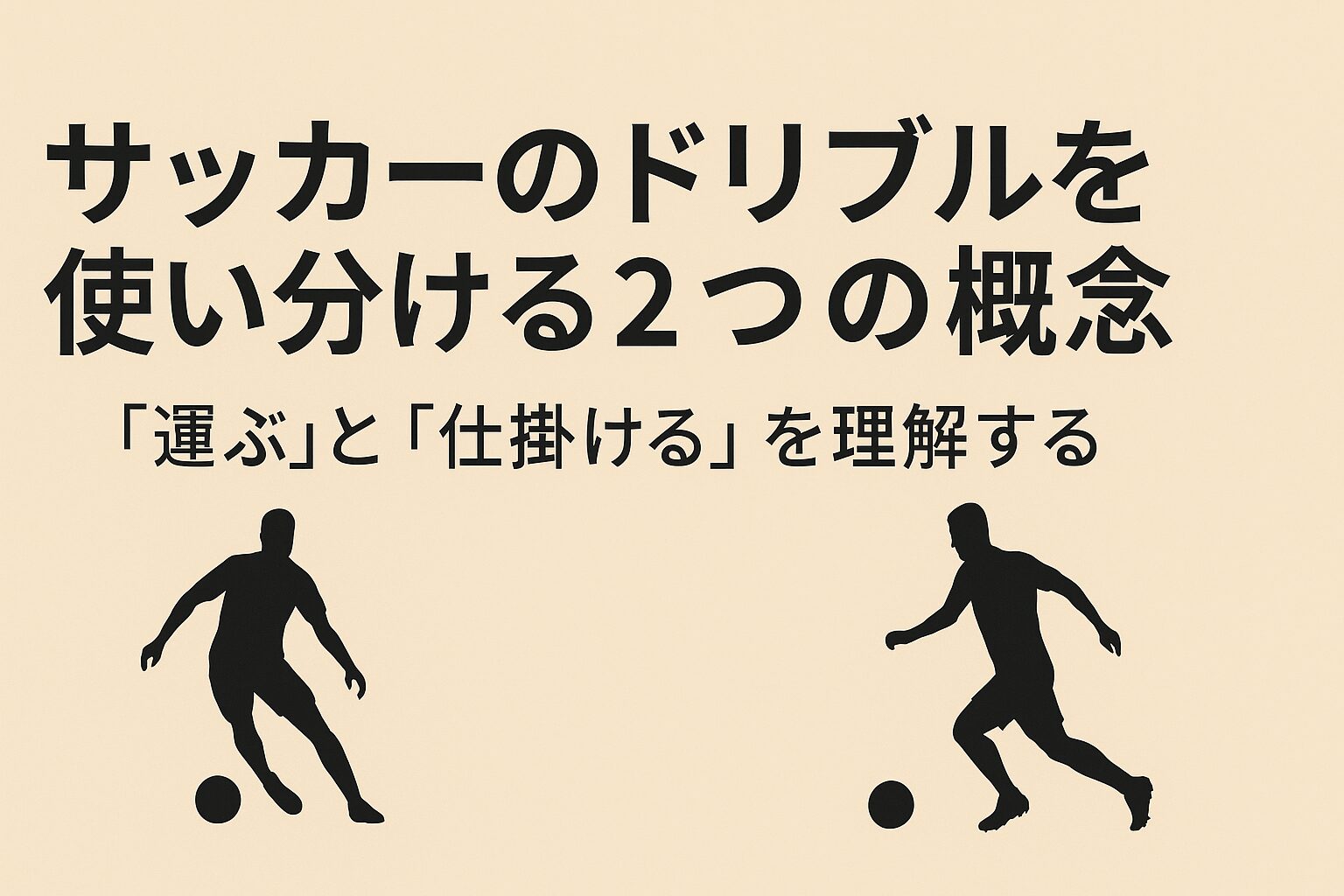

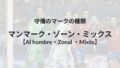
コメント