こんにちは。
今回は、サッカーの“攻撃”の局面における3つのプレーモデルについて話します。
プレーモデルとは、チームのプレーの方針を示すものです。
チームとしてどのような考えをもとにプレーするのか、このプレーをもとにさまざまな戦略を考えることになります。
私は、スペインのマドリッドでサッカー指導者として活動して6シーズン目を迎えます。
過去には、スペイン1部リーグのセカンドチームのスタッフとして活動をした経験もあります。
また、UEFA(ヨーロッパサッカー協会)のサッカー指導者ライセンスも保持しています。
そんな私が、サッカーの“攻撃”の局面における3つのプレーモデルについて話していきます。
攻撃におけるプレーモデルは3つに分けることができる
結論、サッカーの“攻撃”におけるプレーモデルは3つあります。
まずは、その3つを紹介します。
その後、なぜ“攻撃”のプレーモデルを3つに分けることができるのかについて説明します。
1- コンビネーションプレー
ボールを保持しながら、相手ゴールに向かって前進することを目指します。
2- ダイレクトプレー
相手ゴールに向かって、直線的に前進することを目指します。
3- ミックスプレー
上記2つのプレーを1試合の中で使い分けながら、相手ゴールに向かって前進することを目指します。
なぜ攻撃のプレーモデルはこの3つに分けることができるのか?
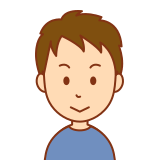
プレーモデルの数なんて、クラブの数だけあるだろう。
もっと言えば、チームの数だけ、それぞれのチームのプレーモデルがあるだろ!
ここで間違えてもらいたくないことは、「プレーモデル」と「ゲームプラン」は異なると言うことです。
簡単に説明すると、「プレーモデル=大枠」、「ゲームプラン=詳細」となります。
そして、サッカーの攻撃の局面におけるプレーモデルを分類するとき、1つの基準があります。
それが「自陣でリスクを冒すか、冒さないか」と言うことです。
では、自陣でリスクを冒すプレーはどちらでしょうか。
自陣でリスクを冒さないプレーは、どちらでしょうか。
・自陣で比較的リスクを冒すプレーが「コンビネーションプレー」
・自陣でリスクをできるだけ冒さないプレーが「ダイレクトプレー」
そして、これら2つのプレーを1試合の中で使い分けるプレーを「ミックスプレー」と言います。
ミックスプレーを選択する理由は主に次のようになります。
コンビネーションプレーがプレーモデルの基本ではあるが、そのためのスペースがないときには、ダイレクトプレーを織り交ぜて、コンビネーションプレーができるスペースを意図的に作り出す。
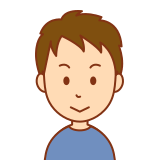
ん?
じゃあ、相手コートまで進んだらどう判断するの?
相手コートでのプレーで、チームのプレーモデルを判断する場合、次のようになります。
・「コンビネーションプレー」→ ボールを保持しながら攻める。ショートパスや横パスが比較的多い。
・「ダイレクトプレー」→ 直線的に攻める。ロングボールや相手のDFラインの背後にボールを蹴ることが比較的多い。
・「ミックスプレー」→ 上記2つのプレーを1試合の中で使い分ける。
プレーモデルを理解することは、自チームのプレー方針を決めるためだけに役立つのではなく、相手チームの分析をする際にも重要なポイントとなります。
なぜ「コンビネーションプレー」と言うのか?
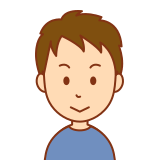
コンビネーションプレーって、名前長いな!
要は、パスサッカーのことだろ?
コンビネーションプレーには、ドリブルもあります。
ボールを保持しながら前進するとなると、おのずとパスの数は増えます。
ですので、パスサッカーと言いたい考えはわかります。
ただし、パスサッカーという言い方をすると、パス以外の手段がプレーモデルに当てはまらないと言うイメージを与える可能性もあり、ここでは「コンビネーションプレー」と言います。
また、「コンビネーションプレー」という言い方は、スペイン語のフエゴ•コンビナティーボ(Juego combinativo)が由来です。
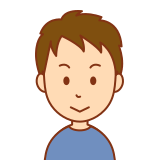
ポジショナルプレーとは違うの?
ポジショナルとは、「位置の、配置の」を意味する単語です。
選手の配置を重要視することが、この名前の由来と考えられます。
実際、スペイン語でもフエゴ•ポシシオナル(juego posicional)と言うこともあります。
しかし、選手の配置は「コンビネーションプレー」だけでなく、「ダイレクトプレー」においても重要なポイントです。
つまり、選手の配置を意味する「ポジショナル」は、2つのプレーモデルを分類する基準とはなり得ません。
ポジショナルプレー ≠ ボールを保持しながら前進
当たり前ですが、「コンビネーションプレー」と「ダイレクトプレー」を使うミックスプレーにおいても、選手の配置はとても大事なポイントです。
まとめ
今回は、サッカーの“攻撃”の局面における3つのプレーモデルについて話してきました。
攻撃のプレーモデルは、以下の3つです。
・「コンビネーションプレー」:ボールを保持しながら前進。自陣で比較的リスクを冒すプレー。
・「ダイレクトプレー」:直線的に前進。自陣でリスクをできるだけ冒さないプレー。
・「ミックスプレー」:上記2つを1試合の中で使い分けるプレー。
これらのプレーモデルを知ることは、自チームのプレー方針を決める時に役立ちます。
プレーモデルをもとに、選手のレベルや特徴、さまざまなことをもとにプレーモデルの詳細を決めていきます。
このプレーモデルの詳細を決めて行く中で、そのチームならではの「プレーモデル」へとなっていきます。
そして、詳細まで決めたプレーモデルをもとに、各試合におけるゲームプランを考えていきます。
プレーモデルの種類を知ることは、自チームを形成するためだけではなく、相手チーム分析にも非常に役立ちます。
相手チームを知る入り口として、大まかな相手のチーム情報を伝えることが大事です。
最初から、相手チーム分析の詳細を話してしまうと、ゲームプランにまとまりがなくなってしまいます。
これを防ぐためにも、プレーモデルの分類は必要です。
「自チームがどのようなサッカーをしているのか」、もしくは、「これからどんなサッカーをしていきたいのか」、また、「相手チームがどんなサッカーをしているのか」、これらのことを考える際に、ぜひ、この3つのプレーモデルについて考えてみてください。
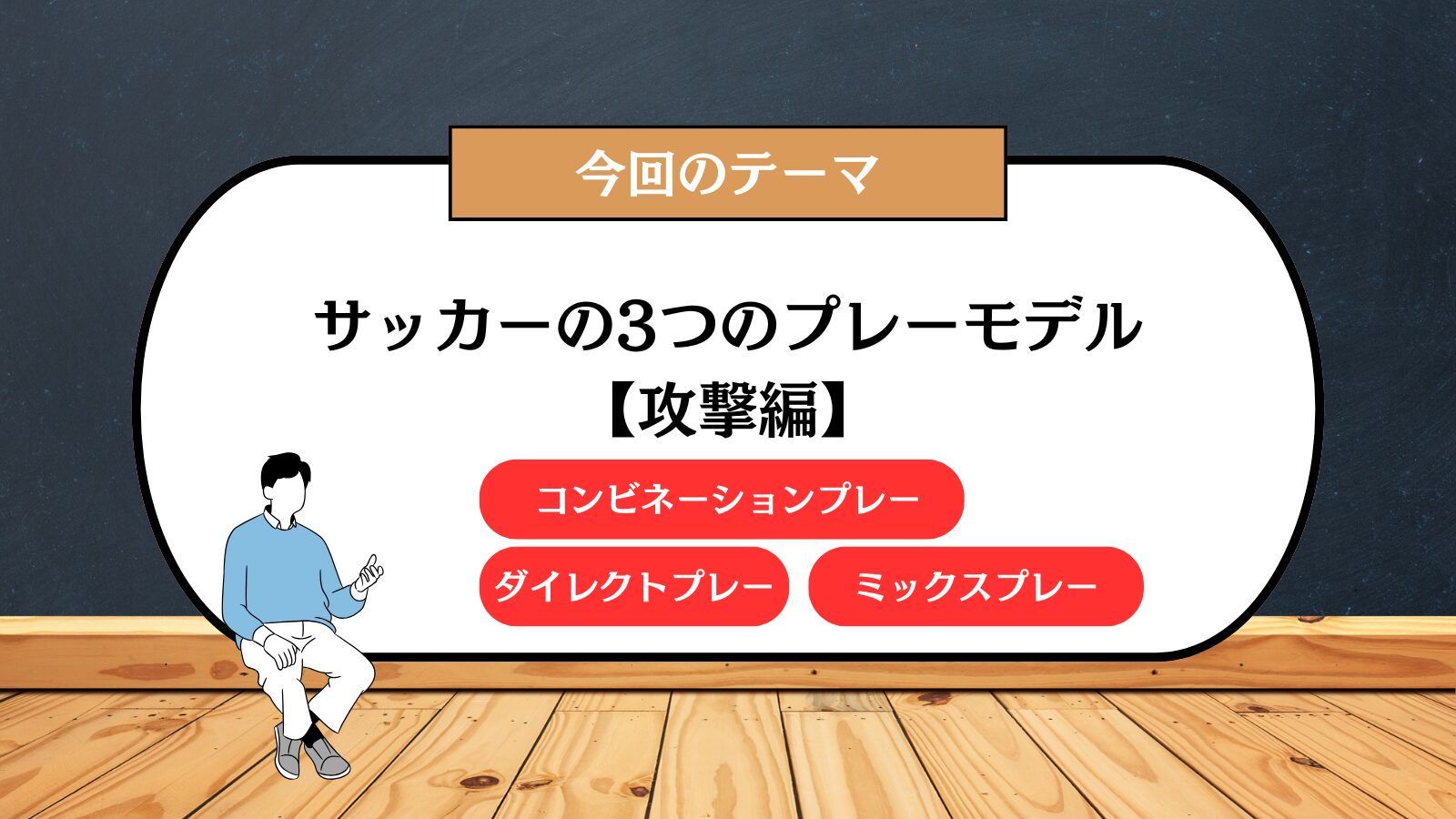


コメント