―“教える”だけでは育たない。選手が自ら考える環境とは?
育成年代の選手にとって、「どんな練習をするか」と同じくらい大切なのが、どんな言葉をかけられ、どう関わってもらうかです。
スペインで6シーズン指導してきて、強く感じたのは──
“教える”よりも“気づかせる”ことを重視する文化です。
1. 知識や判断基準が“前提”として存在している
日本では、プレーの都度「こうするんだよ」と説明することが多いですが、
スペインの現場では「既に伝えたことを前提として話す」場面が圧倒的に多く見られます。
つまり、
「こういう時はこう動く」と事前に教えておくことが前提であり、
指導の現場ではその“判断基準”に照らして選手自身が考えるよう促すのです。
2. サッカーを教えるという“プロセス”がある
スペインでは、サッカーは「体系的に教えるべきもの」として捉えられています。
練習の前提には、
「選手に何を、どの順序で、どの文脈で教えていくか」
という“教育設計”がしっかりとあります。
そのうえで指導中は、
✔︎ すでに教えたことをどう活かせるか?
✔︎ 状況の中で、選手がどの判断を選ぶべきか?
を“問いかけながら引き出す”ことが基本です。
3. 問いかけることで、選手の判断を引き出す
スペインのコーチがよく使うのがこのような質問です:
「この状況、どうするべきだったっけ?」
「Aの選択肢とBの選択肢、どっちが良かった?」
「前に似た場面があったよね?何が違った?」
このように既に学んだ知識を思い出させ、状況に当てはめさせることが、スペイン流の指導の本質です。
“答えを教える”のではなく、“問いかけることで理解を促す”。
その繰り返しによって、選手は自分の頭で考えて判断できるプレーヤーへと成長していきます。
おわりに:問いの質が、選手の質を育てる
スペインの指導は、単なるテクニックや戦術の伝達にとどまりません。
選手自身が「考えること」こそが成長の鍵だという文化が、日常の中に根付いています。
そしてその成長を引き出すのは、指導者の“問いかけ”の力です。
🔜 次回予告
次回は「スペイン式のフィードバック」に焦点を当て、
試合後や練習後に選手へどのように声をかけているのか?を具体的にご紹介します。
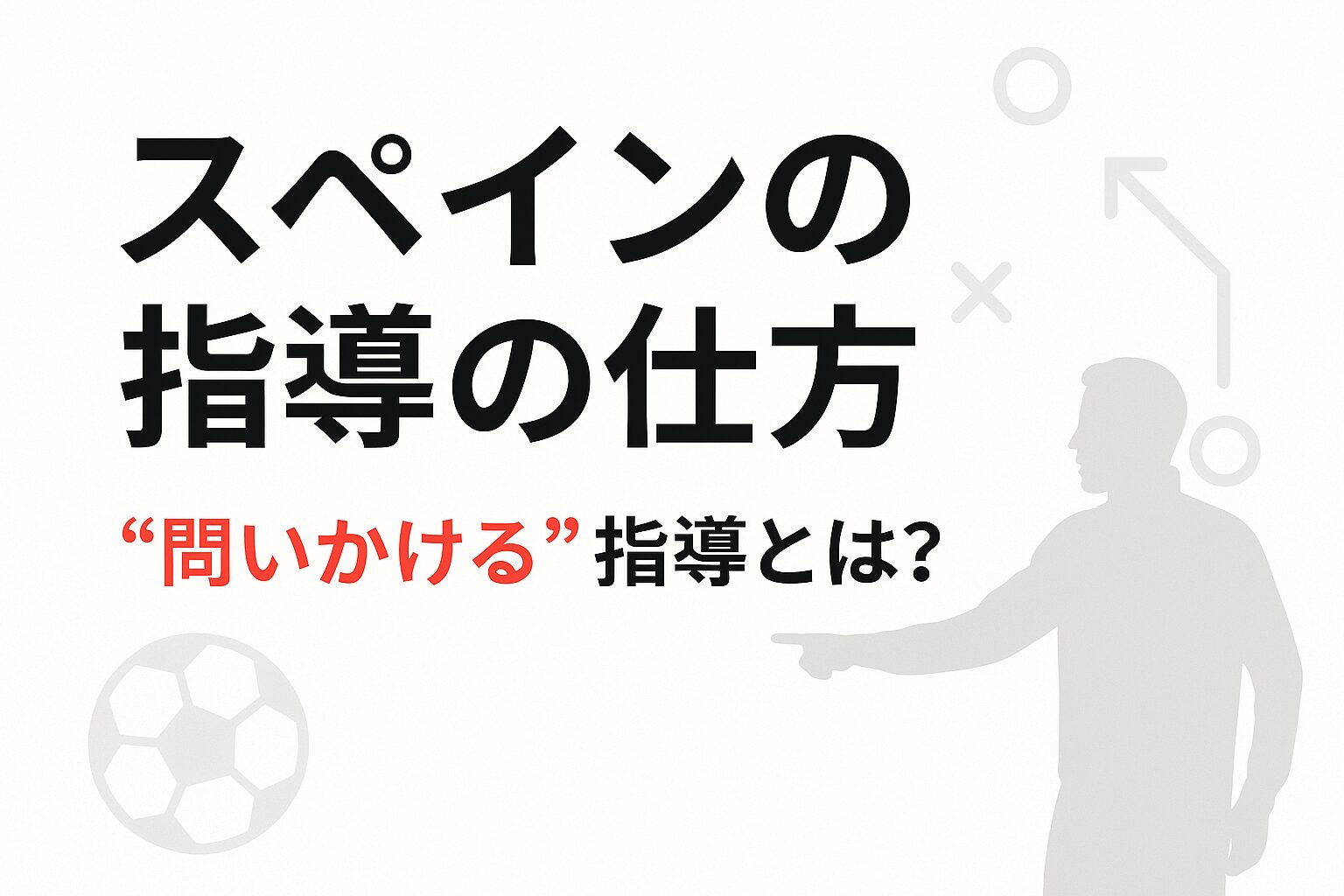


コメント